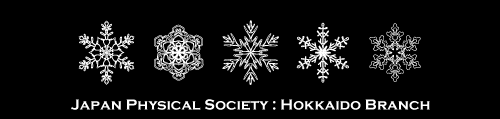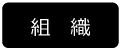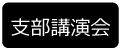"MACROSCOPIC BEHAVIOR OF ACTIVE SYSTEMS WITH A DYNAMIC PREFERRED DIRECTION"
Prof. Dr. Helmut R. Brand
Sep 16, 2011
物理学会北海道支部講演会
講演題目: MACROSCOPIC BEHAVIOR OF ACTIVE SYSTEMS WITH A DYNAMIC PREFERRED DIRECTION
講師: Prof. Dr. Helmut R. Brand
Theoretical Physics III, University(Bayreuth, 95440 Bayreuth, Germany)
日 時 : 平成23年9月16日(金) 13:00-14:00
場 所 : 北海道大学理学部2号館2階 2-211
要 旨 :
We present the derivation of macroscopic equations for active systems with a dynamic preferred direction, which can be either axial or polar. Such an approach is expected to be applicable and important for biological systems, which have preferred directions only dynamically, but not permanently or in a static configuration. For an axial preferred direction we introduce the time derivative of the local preferred direction as a new variable and discuss its macroscopic consequences including new cross-coupling terms. We investigate the coupling to a gel for which one has the strain tensor and relative rotations between the new variable and the network as additional macroscopic variables. For the case of a dynamic polar preferred direction the additional macroscopic variables transforms like a velocity under parity and time reversal. This approach is expected to be useful for a number of biological systems including, for example, the formation of dynamic macroscopic patterns shown by certain bacteria such as Proteus mirabilis.
世話人 北 孝文
(kita@phys.sci.hokudai.ac.jp)
北海道大学大学院理学研究院物理学部門
「固体中の電子に働く多体相互作用の定量評価」
島田賢也氏
Dec 15, 2010
物理学会北海道支部講演会
講演題目: 固体中の電子に働く多体相互作用の定量評価
講師: 島田賢也氏
信州大学教育学部
日 時 : 平成22年12月15日(水) 16:00-17:30
場 所 : 北海道大学理学部2号館2階 2-211
要 旨 :
最近、真空紫外線・軟X線領域の放射光を利用した角度分解光電子分光実験(ARPES)のエネルギー・運動量分解能が向上したことにより、ARPESスペクトルを一粒子スペクトル関数とみなして定量的に解析することが可能になった。原理的にはフェル面上の点を指定し、実験的に自己エネルギーの実部と虚部を導出し、準粒子に働く多体相互作用(電子ー格子相互作用、電子ー電子相互作用)の結合定数を評価できる[1]。私たちは、多体相互作用に由来する自己エネルギーや結合定数を実験的に評価することにより、超伝導や遍歴磁性などの固体物性の基礎的理解を目指している。
これまでに金属の表面準位、バルク準位について多体相互作用の結合定数を評価してきた[2-7]。例えば、アルミニウムの表面準位では、電子ー格子相互作用の結合定数は~0.5、電子ー電子相互作用の結合定数は<0.1であり、電子ー格子相互作用の方が強い[3]。一方、鉄において多数スピンのバルク準位を調べたところ、電子ー格子相互作用の結合定数は~0.2に対して、電子ー電子相互作用の結合定数は~2であり、電子相関がかなり強いことが分かった[4]。ニッケルの結果からは、スピンの向きや波動関数の対称性によって結合定数が異なることが明らかとなった[5]。
ごく一般的に複数のバンドがフェルミ準位を横切る物質(多バンド系)においてはフェルミ面やバンド分散が重なり合うため、精密解析を行うことは必ずしも容易ではない。そこで私たちは放射光の直線偏光特性を活用することに着目した。光学選択則をうまく利用すると入射光の直線偏光面と単結晶試料の鏡映面(=検出面)の幾何学的配置により、観測可能な始状態のブロッホ軌道の対称性を決めることができる。すなわち波動関数の対称性を指定してフェルミ面やバンド分散を分離観測することが可能となる。私たちは、新しい直線偏光依存高分解能ARPES装置を開発し、ルテニウム酸化物超伝導体Sr2RuO4の電子状態の精密解析を行った。その結果、波動関数の次元性に対応して、電子ー電子相互作用に由来す るくりこみ効果が異なること、電子ー格子相互作用の結合定数がフェルミ面に依存して異なること、スピンー軌道相互作用が重要であることを明らかにした[6]。
謝辞:本研究は広大放射光セの岩澤英明、生天目博文、谷口雅樹、広大院理の林 博和、姜健、産総研の相浦義弘、吉田良行、長谷泉の各氏との共同研究です。
[1] Ed. S. Hufner, Very High Resolution Photoelectron Spectroscopy (Springer-Verlag, Heidelberg, 2007).
[2] J. Jiang et al. e-J. Surf. Sci. Nanotech. 7 (2009) 57.
[3] X.Y. Cui, K. Shimada et al., Phys. Rev. B 82 (2010) 195132.
[4] M. Higashiguchi et al. Phys. Rev. B 72 (2005) 214438.
[5] M. Higashiguchi et al. Surf. Sci. 601 (2007) 4005.
[6] H. Iwasawa, Y. Aiura et al., Phys. Rev. Lett. 105 (2010) 226406.
世話人 小田 研
(moda@sci.hokudai.ac.jp)
北海道大学大学院理学研究院物理学部門
「しょっぱい砂糖とスピンの開放」
鹿野田一司氏
Oct 05, 2010
物理学会北海道支部講演会
講演題目: 「しょっぱい砂糖とスピンの開放」
講師: 鹿野田一司氏
東京大学大学院工学系研究科
日 時 : 平成22年10月05日(火) 16:30-18:00
場 所 : 北海道大学工学部A棟 A1-17(物理工学系大会議室)
要 旨 :
二種類の分子が交互に積み重なってできるある種の分子性固体において、中性- イオン性転移という現象が見られる。分子間で電子が移動することによる電子エ ネルギーの損と静電エネルギー(マーデルングエネルギー)の利得が拮抗してい るために、温度や圧力など結晶の環境を変えることにより、"中性状態"と"イオ ン性状態"が入れ替わる現象である。この2つのマクロな状態の入れ替わりが量 子揺らぎとして現れ得ることが、堀内(産総研)十倉(東大)によって指摘され た。私たちの研究室では、この現象を核四重極共鳴という実験手法によって捕ら えることを試みた。この実験方法では、電荷の移動とその揺らぎを高い感度で調 べることが出来る。その結果分かったことが、本題目の意味するところである。
世話人 丹田 聡
(tanda@eng.hokudai.ac.jp)
北海道大学大学院工学研究院応用物理学部門
議事録 平成18年8月18日
Aug 18, 2006
日本物理学会北海道支部支部会日時 2006年8月18日
1.来年度の支部委員
委員長: 村山 茂幸(室蘭工大)
庶務: 河本 充司(北大理)
会計: 三品 具文 (北大理)
会誌編集: 西口 規彦 (北大工)
2.日本物理学会第62回年次大会(札幌地区開催・平成19年9/21~24)の準備状況
について
実行委員長:伊土 政幸(北大理)
副委員長: 根本 幸児(北大理)
北大内スペースの確保
・全学教育の講義室を確保済み
・各部局へスペース確保の働きかけを12月以降(平成19年度スケジュールが
決定後)開始する。文系総合校舎をまとめて確保できると都合がよい。
他大学スペースの確保
・必要に場合によって道工大などのキャンパスを借りる。
*どちらの場合にも比較的高額の使用料が発生する可能性がある。
総合講演会場としてコンベンションセンターを予約(札幌市より援助あり)
・総合講演の後にジュニアーセッションとして一般向けの演示実験を準備中。
アルバイター学生(大学院生が望ましい)50名ほどを確保する。
年次大会開催へ向けて関係者のメーリングリストによる連絡網をつくる。
3.その他
室蘭地区における小中高への出前実験”科学キャラバン”に対して2万円
の財政援助を行う。
以上
「インダクターコアとして用いられるフェライト材料の高度化」
河野 健二 氏
Dec 02, 2004
講演題目: インダクターコアとして用いられるフェライト材料の高度化
講 師 : 河野 健二 氏
(太陽誘電株式会社 総合研究所材料開発部)
日 時 : 平成16年12月2日 (木) 16:00-
場 所 : 北海道大学理学部2号館大学院講義室(2-2-11)
要 旨 :
スピネル型の結晶構造を有する鉄酸化物フェライト磁性材料は、インダクターのコア材として幅広く用いられている材料であるが、近年の電子部品の小型化、高周波化に伴い、フェライト材料の更なる高度化が求められている。
例えば、小型化に伴い、デバイス中の残留応力の影響が顕在化し、デイバス特性を低下させてしまうことが問題になっており、応力に強い材料を開発する必要がある。そこで、我々はフェライトの透磁率が応力に対してどのような振る舞いを示すのかを把握し、これらの知見に基づいた材料開発を行っている。これまでの検討の結果、応力によってフェライトの結晶構造が歪んでおり、応力に対する歪みの振る舞いが透磁率の振る舞いとよく一致することなどが、放射光等を用いた実験から明らかになっている。
また、高周波領域での透磁率特性には、スヌーク限界として知られる特性限界が存在しており、特定の周波数以上では透磁率を得ることができず、今後求められる数百MHz~数GHz帯域で動作するインダクターへの応用上の課題になっている。我々は、フェライトの周波数特性を改善するために、非磁性物質との複合化や、結晶構造が異なるフェライト材料(六方晶フェライト)等に注目した材料の開発に取り組んでおり、これらの材料では、スピネル系フェライトのスヌーク限界を越える特性が得られている。
本講演では、フェライト材料の応力特性および高周波化に対する我々の取り組みについて紹介するとともに、電子部品の小型化、高周波化の流れについても概説する。
世話人 熊谷健一
(kumagai@phys.sci.hokudai.ac.jp)
北海道大学・大学院理学研究科・物理学専攻